家族に給与を支払って節税できる「青色事業専従者給与」を使う際に気になるのが、「専従者給与はいくらまで出していいのか?」という点ではないでしょうか?専従者給与は節税効果が高いため、税務上の注意点が多く、安易に判断すると専従者給与を否認される可能性もあります。
この記事では、専従者給与の基本から届出方法、金額の決め方、実際の節税効果、注意点までわかりやすく解説します。
- 青色事業専従者給与とは?
- 白色申告(専従者控除)との違い
- 専従者給与の届出書・書き方
- 給与の決め方・リアルな実例
- 実際の節税効果
- 配偶者控除はどうなるのか
- 扶養控除はどうなるのか
- 変更方法・ボーナスについて
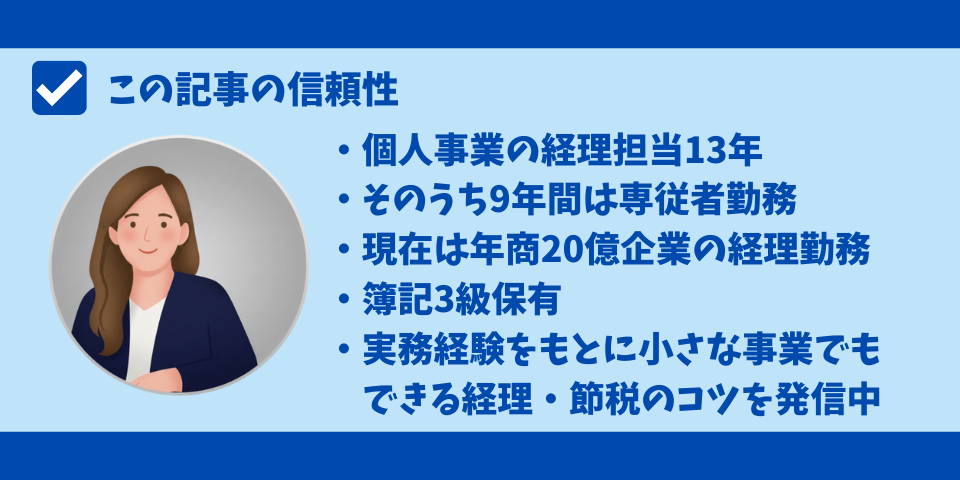
1. 青色事業専従者給与とは?
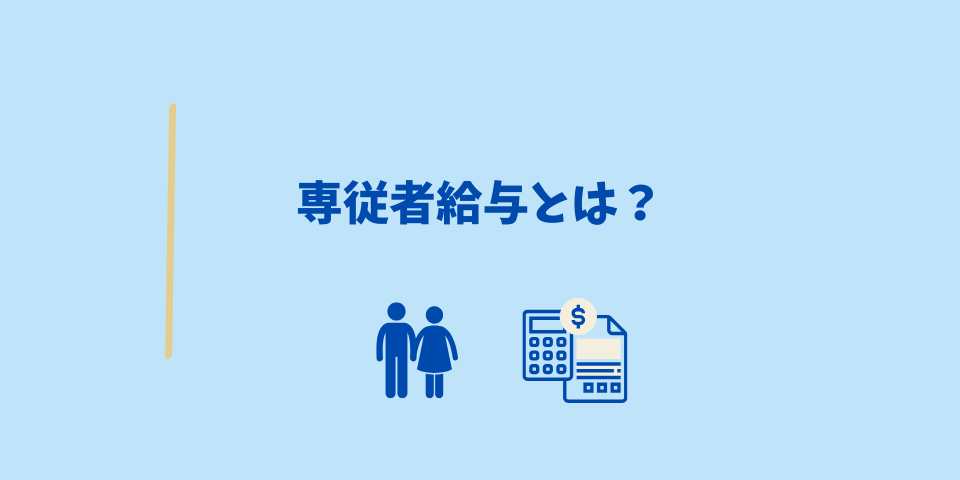
通常は、以下の理由から生計を一つにする家族への給与は経費にできません。
- 「労働の対価」か「生活費」が区別しにくい
- 家族への給与を無制限に認めてしまうと所得の分散、節税が簡単にできてしまう
- 配偶者控除・扶養控除などの配慮があるので家族への給与を認めると優遇の重複につながる恐れがある
ただし、青色事業専従者に対して払う給与(専従者給与)は、所定の条件を満たせば必要経費として計上できます。
専従者給与の要件
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合は事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
(3)届出書の記載方法で支払われ、その記載金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
国税庁:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
補足として、たまに手伝う程度では対象にならず続的に業務をしている人が対象、また、同居していない配偶者や親族であっても「青色申告者と生計を一にする」が満たされていれば対象になります。
2. 白色申告との違い
白色申告でも「事業専従者控除」があり、所得控除ができますが、金額に上限があります。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 控除額 | 払った給与全額 | 年間最大86万円まで |
| 金額設定 | 自由 | 上限あり |
| 届け出 | 必要 | 不要だが要件あり |
青色申告は申請が必要なので面倒に感じますが、申請は1回のみ。
申請すれば、柔軟で節税効果が大きいです!
3. 専従者給与はいくらまで出していいの?
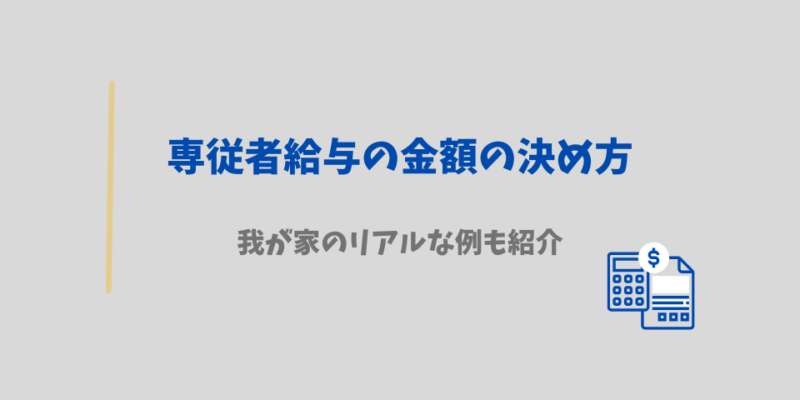
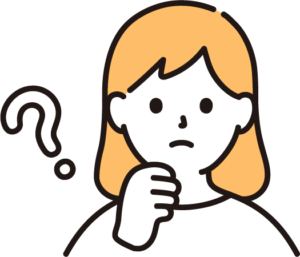
いくらが得なの?



経理するだけでいくらまでもらっていいの?
ここが悩むポイントですよね。
専従者給与は、
- 仕事内容
- 作業時間
- 地域の相場感
- 他業種の相場観
などから、「妥当な金額」である必要があります。



やりすぎると税務署から否認されることも!
▶ よくある実例(所得税・住民税0円)
専従者給与の金額で迷ったらおすすめなのが
【所得税・住民税がかからない年収】
- 所得税:年収103万円以下
- 住民税:年収100万円以下(市町村によっては93万円以下)
ある程度仕事を手伝っているなら月8万にしている人がとても多いです。



税理士さんおすすめの金額!
【節税効果】(所得税率10%の場合)
- 夫の税金:約10万円減!
▶ 我が家のリアルな例
12年間、働き方で専従者給与は都度見直し、
①経理だけ:月8万円
- 妻の所得税・住民税¥0おすすめプラン
②作業も手伝う:月10万円+賞与
- 経理の他に工場の作業も担当
- 勤務時間も増えたので増額
③専従者を辞めてパート勤務:0円
- 専従者よりパートがメインに
→ 専従者給与は使えなくなる
→ 経理は継続(タダ働き…) - 働き方の変化に応じて柔軟に対応!
- 夫の配偶者控除が使えるようになった
- 夫の税金は増えたけど、世帯収入UP + 妻は社会保険加入!
このように、
- 仕事内容
- 家計の方針
- ライフスタイル
に合わせて調整していくのがベストです◎
4. 専従者給与を出すための届出|記入例
専従者給与は、
開業時に専従者給与がいるなら
- 開業届
- 青色申告承認申請書
とセットで出しておくと◎↓
▶ 開業届の書き方と提出方法を解説|freeeやマネーフォワードなら簡単!
▶ 開業届とセットで提出!青色申告承認申請書の書き方・出し方ガイド
▶ 記入例


開業届や青色申告承認申請書に書いたものと同じように記載しましょう。
- 納税地 → 住民票の住所
- 上記以外の住所・事業所等 → あれば記載


②-①:我が家の届出書の実例
②-②:国税庁HP記載の記入例
- 専従者の氏名・続柄・年齢を記入
- 経験年数:業務の経験年数
- 資格等:あれば記載
- 給料・賞与:支払時期、金額を記入
- 昇給の基準:基準があれば記入
金額は仕事内容・作業時間・相場などに応じて記載します。
【ポイント】
- 届出した金額以上を給与で払っても、超えた分は経費にできない
- 賞与は支払えない年があってもOK
- 払う可能性がある場合は書いておく
【我が家の場合】
- 実際払っていたのは80,000円
- 売上に応じて調整できるよう120,000円で届出
- 賞与は売上に応じて支給
- 義母から経理担当を引き継ぎ →「変更理由」も記載
▶ 申請を忘れた場合
その年は専従者給与が使えないので忘れず出しましょう!
翌年から経費にできるようになります。
▶ 年の途中で専従者になる場合
- 結婚して妻が専従者になる
- 会社を退職した家族が専従者になる
など、年の途中で専従者になるケースがあります。
専従者は「1年のうち6ヶ月以上従事する必要がある」のですが、
年の途中からで6ヶ月未満の場合も
例)8月に結婚したなら5ヶ月のうち2ヶ月半以上従事すればOK。



届出は2ヶ月以内に提出!
5. 注意点
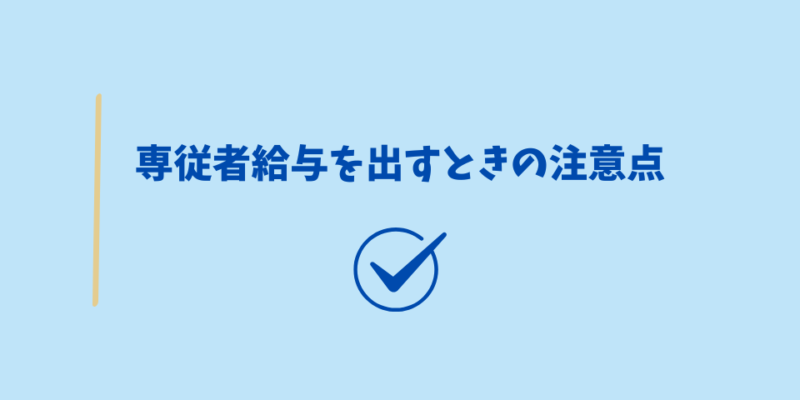
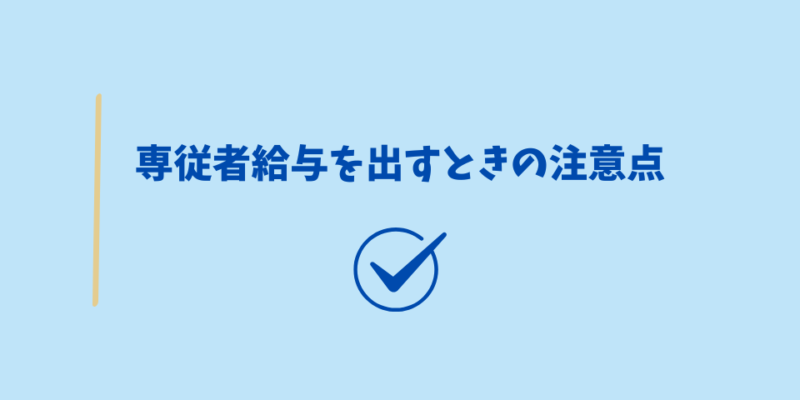
実際に給与を出す場合は、
単に「払ったことにすればいい」というものではありません。
税務署に「実態があるのか?」とチェックされるポイントはこちら↓
- 毎月決まった日に払う(年1まとめてはNG)
- できれば専従者本人の口座へ振り込み
- 給与明細や振込記録を残す
- 必要に応じて源泉徴収や年末調整する
- 給与の支払いは毎月25日
- 毎月銀行でおろして通帳記帳+メモ
- 年末に源泉徴収
6. 【節税】国保・所得税・住民税の変化
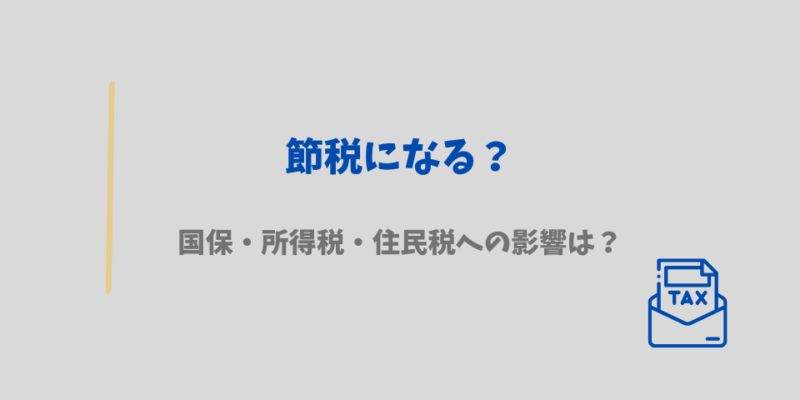
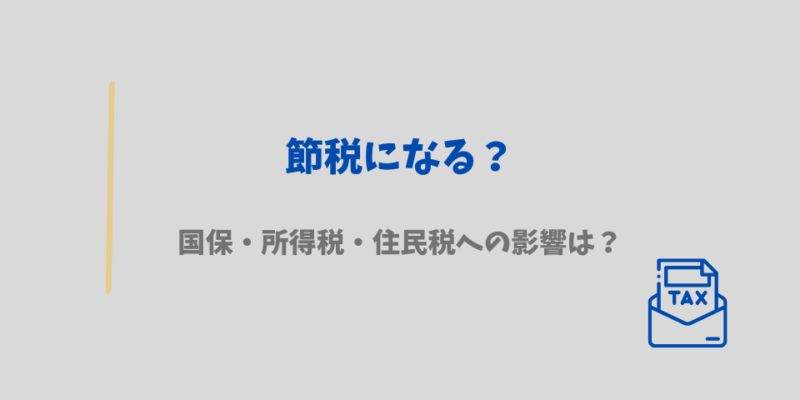
よく誤解されがちなのが、
国民健康保険は
- 世帯単位で計算される
- 専従者給与で夫の所得を妻に分散しても、国保の保険料は大きく変わらないことが多い
でも、
所得税・住民税は夫婦別々に計算されるので、全体で見ると節税効果は大きい!
▶専従者給与0円/96万円での税金比較
【前提条件】
- 夫婦2人世帯(子どもなし)
- 基礎控除
- 配偶者控除は夫400万円の場合のみ
※妻が1円でも専従者給与をもらっている場合、夫の配偶者控除は使えなくなるので注意
| 項目 | 夫:400万円/妻:0円 | 夫:304万/妻:96万 |
| 所得税(夫) | 221,000円 | 161,800円 |
| 住民税(夫) | 307,000円 | 244,000円 |
| 国保 | 571,300円 | 447,600円 |
| 個人事業税 | 87,500円 | 39,500円 |
| 計 | 1,186,800円 | 892,900円 |
その他控除が入っていないので実際はここまで税金はかかりませんが、
- 妻の所得が0円の場合、国保の基礎控除は1人分(43万円)のみ
- 所得を分散するだけで国保の基礎控除が2人分(86万円)になる
→だから国保料も13万安くなっている◎
7. よくある質問
Q1. 専従者給与の上限はいくらまで?
A. 「法的な上限」はありません。
でも、事業の種類や専従者の役割によって「労務の対価として相当」と認められる金額でなければ経費にできません。
同業他社の給与などを参考にするのもおすすめです。
Q2. 専従者給与は毎月変動してもいい?
A. 毎月定額でないといけない決まりはありません。届出した上限を守ればOKです。
Q3. 専従者給与が事業主の所得より多くなってもいい?
A. 通常専従者給与の方が高いケースはあまりありませんが、以下のケースは認められる場合があります。
- 事業主が高齢・病弱で専従者が重要な仕事を担当しているようなケース
- 災害・貸し倒れなどで所得が減少した場合など
我が家は1年だけ夫の所得の方が低くなったことがありますが、
- その年は農業の赤字が大きかった
- 事業規模が小さいと税務調査は入りにくい
ことからか、税務調査に入られることはありませんでした。
Q4. 事業主が赤字の場合、専従者給与はどうなる?
A. 貸し倒れや災害、景気変動などで赤字になった場合、相当な理由があるなら専従者給与は全額経費になります。
でも毎年赤字になるようなら、専従者給与を支払うこと自体を検討する必要があります。
Q5. 専従者給与の金額変更はどうすればいい?
A. 「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を「すぐに」出しましょう。
提出期限は決められていませんが、「遅延なく」と規定があるので、早急に出しましょう。
専従者が増える場合も「変更届」を出しましょう。
Q6. 専従者にボーナスは出せる?
A. 「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」の「賞与」の欄に記入していれば、賞与を出しても経費と認められます。
賞与はその年にの業績に応じて出せなくても問題はないので、出す可能性があるなら申請しておきましょう。
Q7. 専従者を途中でやめるとどうなる?
A. やめた時点で経費計上をやめましょう。特に手続きは必要ありません。
- 専従者給与を出さなくなると、事業主の配偶者控除が使えるようになる
- 配偶者控除は専従者でなくなった翌年から適用される



パートで働き始めた翌年から夫の配偶者控除が使えるようになりました!
Q8. 専従者が年金受給中でも給与は経費にできる?
A. 年金受給中の家族でも、青色事業専従者の要件を満たせば経費にできます。
例)事業主が同居の母(年金受給中)を専従者にするようなケース
- 年金受給中かどうかは専従者給与に影響しない
- 実際に事業に従事している必要がある
- 年金(雑所得)+給与所得で所得税が計算される
- 専従者給与を受け取ると、事業主の扶養控除が使えなくなる
Q9. パート掛け持ち・副業しても専従者のままいられる?
A. 働き方によっては専従者のままでいられます。
こちらの記事で詳しく解説しています↓
▶ 専従者とパート・副業は掛け持ちOK?条件・具体例・注意点を徹底解説!
まとめ
- 青色申告をしていれば、配偶者や家族への給与を経費にできる
- 専従者給与は届出・妥当な金額・毎月の支払いがポイント
- 税金は節約できても、国保は世帯所得ベースなので注意
- 家計やライフスタイルに合わせて、柔軟に運用すべし!
「家族に給料を出す」ってハードルが高く感じるかもしれませんが、手続きすれば合法&超効果的な節税手段です。



最初は不安だったけど節税効果は絶大!
せっかく仕事を手伝うなら自分の労力を節税にダイレクトに活かしましょう♪
自営業妻の扶養や年金もよく分からない…そんな方はこちらを読めば解決できます↓
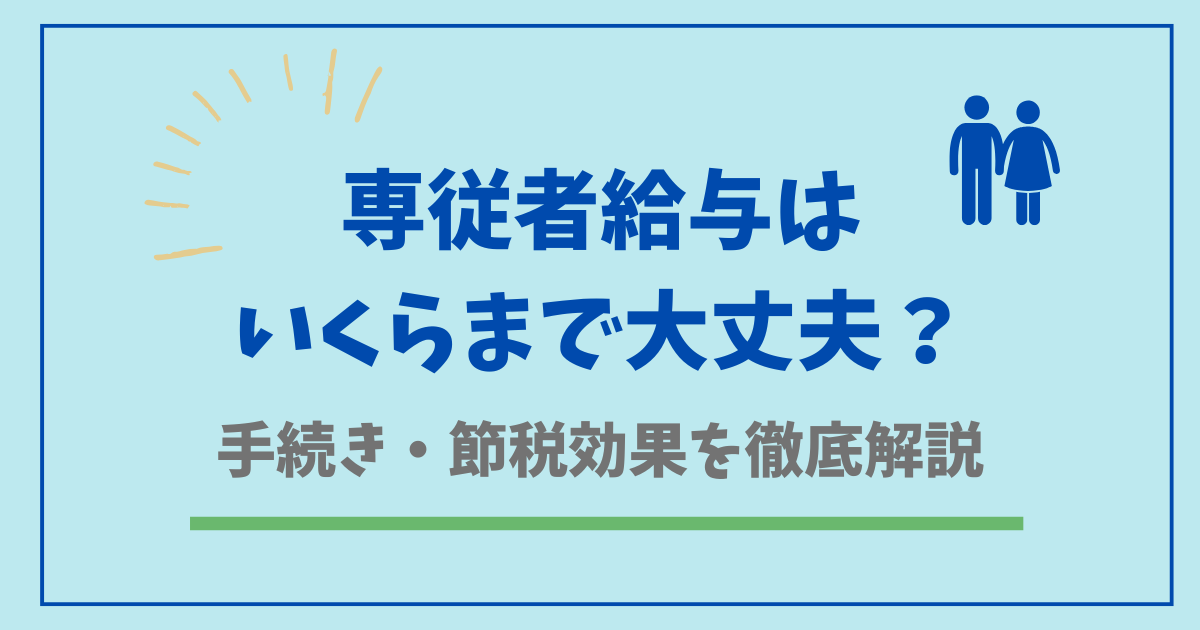
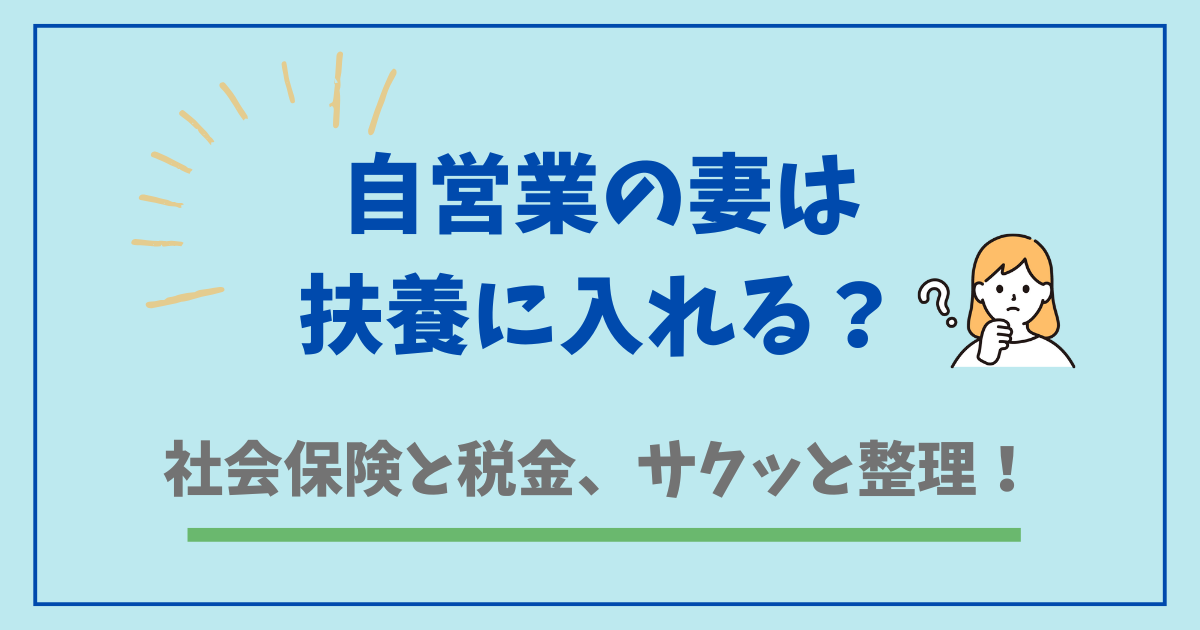
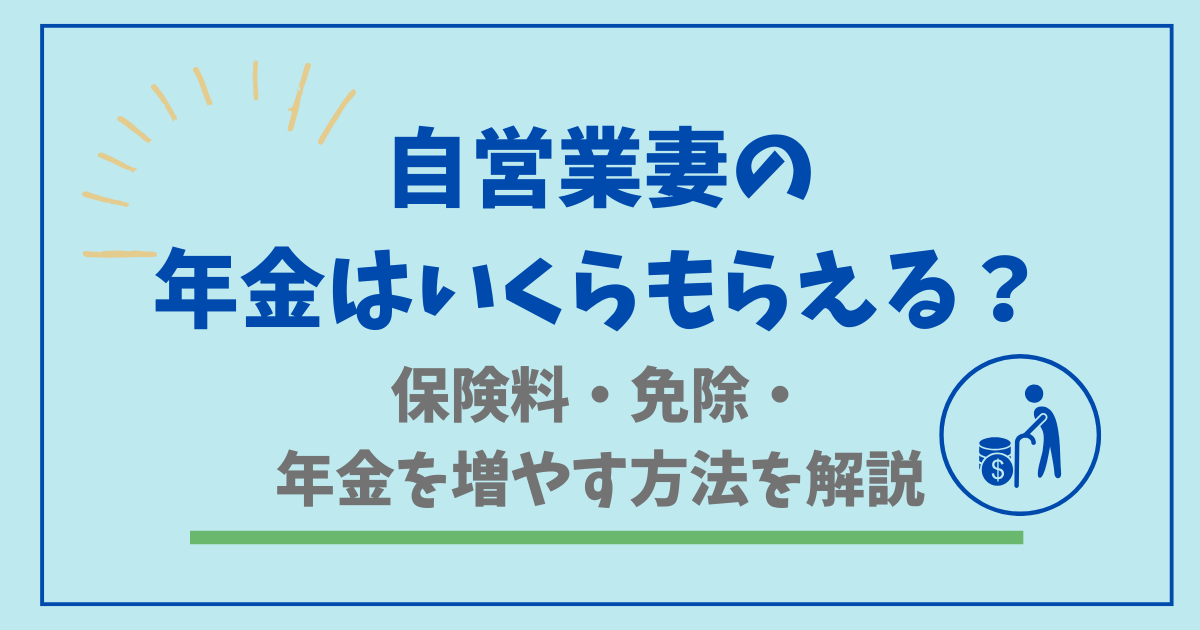
コメント